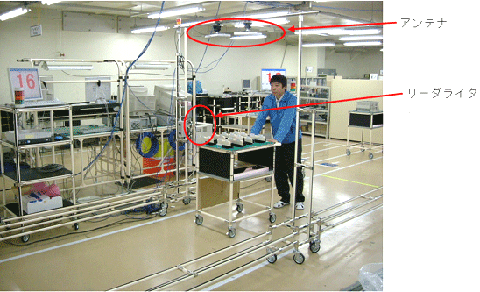RFID(Radio frequency Identification Tag)
無線ICタグ、情報を記録するICチップと金属製のアンテナで構成する装置の総称。ICは0.1ミリ~数ミリ角の大きなであるから、ゴマ粒チップとも呼ばれる。
一つひとつのものに固有のIDを振ることができ,ある程度離れた場所から複数のもののIDを一括して読み書きできることが大きな利点。商品の位置と数量を正確に把握できるため,物流拠点での検品や小売店での商品補充などの応用が期待されている。
ICは10数バイト~数Kバイトのメモリーとロジック回路を備え,無線通信によってデータの読み取りや書き込みができる。ロジック回路によって,演算,認 証,暗号化などの処理もできる。データの読み書きを行う装置をリーダー/ライターと呼ぶ。通信距離は数cmから2mぐらい(国内)。無線ICタグは,電池 を内蔵するものとしないものがあるが,現在は電池を内蔵しないものが主流。電池を内蔵すれば,無線ICタグから能動的に情報を発信することもできる。記録 するIDには,ものの属性情報などを直接含めないこともある。この場合はIDと属性情報を関連づけるためのデータベース・サーバーが必要になる。
無線周波数は 13.56MHzと2.45GHzが国内では有力。13.56MHzは電磁誘導方式を,2.45GHzはマイクロ波方式を用いる。電磁誘導方式は,リー ダー/ライターのコイルに電流を流して発生させた磁界で,無線ICタグが持つコイル状のアンテナに電流を発生させ,ICチップを動かす。マイクロ波方式 は,リーダー/ライターのアンテナから発生させた電波を無線ICタグのアンテナで受け取る。どちらにしても無線を使うという特性上,無線ICタグの付近や リーダー/ライターとの間に金属や水があると悪影響を受ける可能性がある。通信距離には日本の電波法の規制があり,13.56MHz帯で70cm程度, 2.45GHz帯で1.5m程度。2004年後半には,規制緩和により950MHz前後(UHF帯)の周波数も使えるようになる見込みである。このほか, 125k~135kHzの周波数も使われている。
| 無線ICタグ | バーコード | |
| 記録できるデータ量 | 大きい(数十Kバイト) | 小さい(数バイト)* |
| 最大通信距離 | 2m前後(国内) | 50cm前後 |
| 不正な複製 | 困難 | 容易 |
| 経年変化や汚れ | 耐性が高い | 耐性が低い |
| 一括読み取り | 容易 | 困難 |
| コスト | 高い(数十円以上) | 低い(ほぼ0円~数円 |
JR東日本が導入している「Suica(スイカ)」などの非接触ICカードも,無線ICタグと同じ仕組みである。商品に貼り付けるタグと人が持ち歩くカードでは,利用形態が異なるものの,ほぼ同じ技術を使っている。
◆効果
検品作業を効率化
RFIDタグは、微弱な電波を発して読み取り機と情報をやり取りします。タグの中には、ID番号(識別子)が入っており、バーコード代わりの役割を果たします。識別子しか入っていないタイプのほかに、タグのなかに情報を書き込める方式もあります。
実際の利用では、事前にID番号と商品の属性などをひも付けた情報をデータベースに登録します。ID番号が分かれば、その商品の色やサイズといった情報が把握できます。
アパレル業界では、検品作業の効率化にRFIDタグを活用し始めています。百貨店などの売り場では、バーコードを利用した検品作業に大きな手間が かかっています。シャツのように折り畳まれた商品の場合、1点ずつ袋から出してバーコードを読み取らなければならないからです。RFIDタグを取り付ける ことで納入された商品をなぞるだけで検品が可能になります。
さらに、物流分野に適用が期待されているのが、UHF帯の電波を使ったものです。電波の届く距離が数メートルと長いため、倉庫や港湾など広い場所で一度にコンテナを読み取るといった使い方が可能になります。
◆事例
売り逃し防ぐ
阪急百貨店は今年4月、うめだ本店の靴売り場にRFIDタグ2万枚を導入しました。卸業者が、RFIDタグを靴に取り付けて納品しています。倉庫に読み取り機を設置し、在庫状況が店頭で即座に把握できる仕組みです。
同店の店頭では、各商品につき1サイズしか展示せず、残りの在庫は少し離れた倉庫にあります。従来は、顧客が望むサイズの在庫状況は倉庫まで行かないと分からず、往復に5分ほどかかるため顧客を待たせてしまい効率化が必要でした。
RFID導入後は、店員は携帯端末で店内にある倉庫に加えて、卸業者にある在庫も確認できます。これによって店員は接客に集中できるうえ、卸の在庫を確認できることで売り逃しも防げます。
無線タグの仕様は用途やメーカーごとに違うが,業種や国境を超えた利用の拡大やインターネットとの連携を想定して標準化の動きも進んでいる。無線インタ フェースやプロトコルの標準規格としては,ISO 18000があるが,無線周波数の違いなどでISO 18000-1から同18000-7までの種類がある。無線タグに搭載するデータのフォーマットは,米EPCグローバル(旧・オートIDセンター)の仕様 「EPC」をベースに2004年前半にもISO規格化される見通しである。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/rfid/index.html